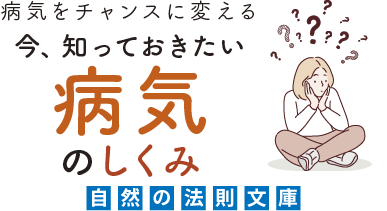人類は、その誕生以来、ほとんど生物的には進化していません。外見も脳の容量もほとんど変わりません。人類の歴史は、道具の進化の歴史でした。自分自身の変化が少ないにもかかわらず、道具と、それを用いた生活がものすごい勢いで変化していったわけです。とくに、産業革命以後のここ150年あまりは、異常なほどの変わりようでした。
このギャップが、社会生活を営む私たちにストレスという形で押し寄せてきているのです。不規則な生活、汚染された環境、コントロールできないほどのスピード化、さまざまな社会条件のなかでの意志の束縛等は、人類がかつて味わったことのない環境といえます。したがって、現代社会のなかで健康を考えるためには、ストレス対策ということが重要なカギになっています。
本来、動物にはけがはありますが病気はありません。
しかし、動物病院の繁盛ぶりからもわかるように、これら病気をしないはずの動物たちも、人間に飼われると、決まって人間と似た内臓病をもつようになります。病気のない動物も人間に飼われると人間に似てくるのです。
その動物たちの病気の原因とはいったい何でしょうか。
それは、ストレスなのです。動物は大自然の中で生きていくという法則から離され、人間に飼われることによって、動物本来の、生きていくリズムを失ってストレスにかかってしまうのです。
それでは動物がもっているはずの本来のリズムとは何でしょうか。それは簡単なことですが、動物が〝動物らしく〟自然の中で自然にふるまうことです。
私たちは、動物にもう一度学ばなければならないところまで来たのです。
その昔、人間も本来、動物のように自由でありのままにふるまい、自然と同化しながら生きることもできていました。その頃にはストレスもあまりなくて、病気を恐れることもなかったはずです。
日本には、1万年という長期にわたった縄文時代があり、そこでは戦いはなく、共存共栄の時代であったという考察もあります。
ところが、人間が進化して文明を得て以来、さまざまな理屈が出てきて、人間は不幸になってしまったのです。
では、動物からわれわれは何を学ぶべきなのでしょうか。
もちろんありのままの大自然の法則です。大空を飛ぶ鳥や大地を走り回る動物には〝病人〟はいません。けがはしますが病気にはならないのです。
彼らは成長すると、自然に大空へ、大地へと巣立っていきます。鳥や動物たちは、飛びたいときに飛び、走りたいときに走り、そして食べたいときに食べ、眠りたいときに眠っています。
つまり大自然の法則のなかでやりたいように生きているのです。だからストレスがありません。病気になる要因がないので病気にならないということです。
ひるがえって人間を考えてみましょう。人間の母親は、もうとっくに大空へ羽ばたいていなければならない自分の息子と娘を自分のそばにおいて猫かわいがりをします。
人間の子どもたちは親の愛情と錯覚しているエゴによって、大空へ、大地へ飛び出すタイミングを失ってしまっているのです。
生まれたままの赤ん坊が、やがては自由に這いまわり、走りまわるように、自由で自然な人間には、本来病気などはなかったはずなのですが。
かつて、昭和の初期まで人々はほとんど医者にかかりませんでした。いや、かかろうとはしなかったのです。
医者を呼ぶのは伝染病にかかったときくらいでしたから、死亡率も高かったのです。しかし、ここで肝心なのは昔の人のほうが、いまよりもはるかに自然治癒力を身につけていたといえます。
たしかに、いまはそういう感染病の細菌は地球上から少なくなりました。ですから、そこに来るまでの医学の発達はたしかに目ざましいものがあったのは事実です。
ですが、それ以降、医学は少しも進歩していません。
いまや、人間の病気は〝心因性〟のものにすっかりとって代わっているのです。なのに、近代医学は、いまだに対症療法が中心で〝外因性〟のものだけを追いかけているのが現状なのです。
じつは、いまの時代は、病気にかからなくてもいいはずの人たちまで病気になっています。自分で病気をつくっていると言い換えてもいいでしょう。
前向きにものを考えればいいものを、じっと座って考えこみます。何かが起こればすぐに何かにすがろうとします。
人のやっていることがやたら気になったり、ほんのささいなことで他人を恨んだりします。すると、身体の中の正常なリズムが正常でなくなり、変調をきたしてくるわけです。血管は収縮し、心臓は圧迫されます。
現代では社会の仕組みや環境に左右されながら、心の問題を抱えて、病気がつくられていくのです。
薬や手術で無理に血管を拡げたり、心臓に活力を与えても、それはほんの一時的な効果しかもたらしません。またすぐに元の木阿弥です。
こうした人間の心因性の部分に、人間に飼われる動物までが、大自然のリズムをなくすことによって影響を受けていきます。
動物で病気になるのはペットや家畜だけなのです。