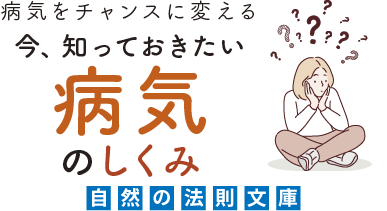現代医学では、がん対策として、がんの早期発見とがん細胞の早期撤去、そして手術後の放射線治療が主流となっています。
その根拠になっているのがドイツの病理学者、ルドルフ・ウイルヒョウの細胞分裂説です。
ウイルヒョウは1859年に「すべての細胞は細胞分裂から生まれる」という学説を発表し、それがその後の生物学、医学の定説とされて今日に至っています。
がんでいえば、がん組織には必ず正常と異なるがん細胞があり、それが細胞分裂を繰り返してどんどん増えていくという説明です。つまり、がんの元はがん細胞で、がんは必ず局所から発生し、それが勝手に猛烈な勢いで分裂増殖していくというわけです。
ウイルヒョウの唱えたこの「ガン局所説」は外科医たちを大いに勇気づけました。なぜなら、がん細胞が細胞分裂によって増殖していくのだとしたら、その元になるがんの局所(がん組織)をごっそり摘出し、その後、化学療法、放射線治療でがんという悪魔を抹殺すればよいと考えたからです。
その結果、果たしてがんは根絶できたのでしょうか。否、がんはますます猛威をふるい、年々がん患者は増加して、日本だけで年間30万人以上ががんで亡くなっているのです。ということは、いまのがん治療のよって立つがん理論そのものが間違っていると考えざるをえないのです。
その原因は、人工的な環境下(顕微鏡観察)で見える分裂像がすべてと錯覚し、細胞分裂説を絶対化してしまったことによります。がん細胞が分裂像を示すのは事実であるとしても、それはあくまでも異常行動にすぎないのに、その一部的な側面をもって、すべてを決めてしまったことによるのです。
東大名誉教授で日本免疫学会の会長を務めた多田富男博士は自著『生命の意味論』において、次のように述べています。難しい部分がありますが、そのまま引用します。
「細胞は、刺激が与えられた瞬間の文脈を判断し、異なった行動様式をいくつかのオプションの中から選択している。実は細胞は、刺激を受けた自分がおかれている『場』がどのようなものであるかを同時に認識しているのだ。正当な場に置かれた時のみ『正』の反応を起こすように仕組まれているのである。場が形成されていない場合には『負』の反応しか起こさない。それは、条件によって異なった行動の選択をする。
生体は、こうした『場』と『時』に応じた細胞の選択が集積されて、はじめてうまく運営されている『複雑系』ととらえなければならない。生命は、DNAから細胞に至るまで、あいまいさに裏付けられて動いていた。実はそのあいまいさゆえに、生命は『回路』を外に開いて、動的に活動することができたのである」
実際、今の生物学では、細胞自体が瞬時に「いま自分がどんな場に置かれているか」を認識して、正当な場に置かれたときには正の反応を起こし、正当な場が形成されていない場合には負の反応しか起こさないというところまでわかってきているのです。
だとしたら、人工的な環境での顕微鏡観察で細胞分裂の像が見られたからといって、それを普遍化・絶対化してしまうというのはおかしな話になります。
なぜなら、生体内での自然な状態と顕微鏡観察時では、細胞の置かれた「場=環境」がまったく違っているからです。
そして、細胞や血液の「あいまいさ」をだれより、何よりも重視して観察していたのが、のちに詳述する生物学者、千島喜久男博士だったのです。多くの研究者は「科学とは明解なもの」と認識する立場から、不確実なもの、あいまいなもの、漠然としたものは大胆に切り捨ててしまいましたが、千島博士は、「あいまいに見える限界(中間)領域にこそ、重大な発見のカギが隠されているに違いない」という姿勢から、AともBともつかない漠然とした中間的な領域の現象を、地道に丹念に観察していきました。
その結果、赤血球が細胞に分化していく事実を見出し、細胞や細菌が自然発生することを発見し、腸で赤血球がつくられていることを発見したのです。
そして、千島博士は「境や区別というのは人間が作ったもので、自然界には本来、境などないのだ」と言うのです。