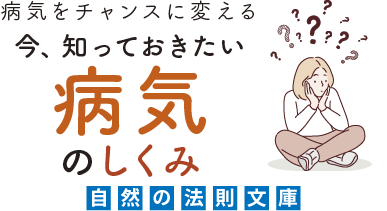日本尊厳死協会副理事長である長尾和弘医師は、最初に配属された救急病院で、肝硬変やがんの末期症状で苦しみながら亡くなる多くの患者の最期をみとった経験から、本来の人生の最期とは何かを真剣に考え、次のように書いています。
病院医療では、腕や身体には点滴の管、鼻には吐き戻したものを吸い出す管、尿道にはおしっこを抜く管。ほかにも酸素マスクや心電図モニターをつなぐ管など、まさに絵に描いたような管だらけの姿で死んでいく人がなんと多いことか。そんな中で、枯れるような〝自然な死〟を病院医療と在宅医療の両方で見たことが、私と「平穏死」との出会いになりました。
私が、在宅医療を受け持った患者さんが胃がんで、その患者さんは自力で食事ができませんでした。となると普通なら高カロリー点滴をするのですが、この時はしないことになりました。すると枯れるように、しかもモルヒネなどの医療用麻薬をまったく使わずに亡くなりました。
このように終末期には、過剰な医療を行わずに自然に任せれば、大きな痛みが少ないので医療用麻薬もあまり使いませんし、血も吐きません。そして最期まで何かを口から飲んだり食べたりすることができるのです。
「真に理想的な死」とは死に向かっていく経過が10日間くらいある場合でしょう。介護が必要な状態が10日間くらいであれば、仕事があるご家族でもお世話をすることが可能でしょうし、知人のお見舞いを受けたり、お別れの言葉を交わしたりすることができます。ご家族がお葬式の準備をすることもできます。
いっぽうで、「平穏死」には明確な闘病期間があります。末期がんの終末期でも、毎日水を500ミリリットルくらい飲めれば、数か月ほどは自宅で過ごせるのです。その間には外出をしたり、家の中を移動してトイレに自分で行けたり、口から飲んだり食べたりすることができます。そして何よりも、会話で意思疎通を図れることが重要です。
尊厳を保ちつつ緩和ケアを行って寝込む期間と苦痛を最小限にする、それが「平穏死」や「尊厳死」の概念なのです。
ここまででわかるように、終末期に〝苦しまずに死ぬコツ〟は、点滴をしないことです。脱水状態にすることで、身体がむくむこともなく楽に動けるし、話せるし、何かを口に入れることができます。これは末期がんでも老衰でも同じなのですが、医学部では教えてくれません。
終末期なら過剰な医療を控えるだけで穏やかな死が実現するのに、ほとんどの医師がそれを知らないため、延命治療のフルコースを施し、いくつも管をつないで命を長らえようとするわけです。
また、点滴に大量に入っているブドウ糖はがんの大好物なので、点滴をすればするほど腫瘍がぐんぐんと大きくなっていきます。最期の時が迫っているのに水分や栄養をたくさん体に入れてしまうと、顔や体がパンパンにむくんで苦しみながら死ぬことになります。
欧米ではすでに、「緩和医療とは脱水状態にすることだ」と明言されています。脱水といっても人工的に水分を抜くわけではなく、「脱水になるのを見守る」「脱水を容認する」ということなのですが、日本ではそういう教育がまったくできていないのが現状です。
まだまだ終末期医療が未成熟な日本では、「理想の最期を迎えたい」という願いがかなえられるのは半数以下です。しかし、元気なうちからしっかりと理想の最期について考え、「延命治療をしない」という意思表明をしておくことが、その願いをかなえる第一歩になることは間違いありません。