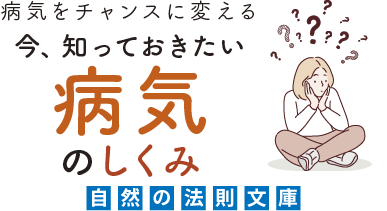以下の文章は稲田義弘著『「ガンの呪縛」を解く』から抜粋、引用した内容です。
千島学説の生みの親である千島喜久雄は、それまでの中学教師を退職して41歳から遅まきながら九州大学農学部で研究人生を歩み出しました。そこでの研究テーマである、ニワトリの卵を題材にした「胚の発生」の研究プロセスで驚くべき発見をしました。その発見とは、赤血球が原子生殖細胞や生殖腺のすべての細胞に分化、移行していたことでした。
それまでの定説ではドイツのウイルヒョウの説をもとに、「生殖細胞は分裂増加する」と言われていたのに、事実はこれに反して赤血球から生殖細胞などが生まれていることを、千島博士は顕微鏡観察によって発見したのでした。
「細胞は細胞の分裂によって生じる」というのがそれまでの定説で、それが生物学のもっとも重要な根本原理とされてきました。たしかにいまの学校教育ではそのように教えていますし、私(著者)自身もそのように学んできました。
千島博士は念には念を入れて何度注意深く顕微鏡を覗いてみても、明らかに赤血球から細胞が生まれていたのです。
他の研究者と千島博士の決定的な違いは、顕微鏡で見る場合の「標本の作り方」の違いにあったのです。
「生殖腺を中腎から切り離して作った標本」と「切り離さずに中腎と生殖腺を一体とした標本」の違いなのですが、この両者で決定的に違ってくるのは「平常時」と「異常時」の違いなのです。
千島博士がやったように、中腎と生殖腺を一体とした標本の場合、生殖細胞は安心して本来の活動を続行することができますが、他の研究者のように中腎から切り離して生殖腺だけを単独に取り出すと、生殖細胞はそこに異常な環境変化を感じ取って異常な活動を始めます。危機状態に直面した細胞は、平常時とはまったく違った活動を開始するのです。
しかし、これまでのほとんどの生物学者たちは生命のその基本を無視し、もっぱら細胞や血液を「全体」から切り離して観察し続けてきました。しかし、細胞や血液は体全体とつながって生きてきているものであって、それを無視した観察から「ほんとうのいのちの営み」を見ることはできません。異常な状態に置かれた細胞や血液は、当然のことながら異常な反応を示すからです。
にもかかわらず、これまでの生物学や医学は、その異常状態での反応を絶対化し、それを「定説」として理論体系を組みあげてきました。そしてその結果、気がついたらとんでもない錯覚の学問体系を構築してしまっていたのです。
千島博士は、さまざまな動物を使って観察し続けました。そして、肝臓でも、脳や神経、皮膚、筋肉、骨なども、すべての細胞や組織が赤血球から変化してできることがわかってきました。そして、がんは病的な血液ががん細胞化しているということがわかったのです。その意味で、がんとは血液が劣化・悪化・病的化した結果の現象であって、がんはいわば「全身病」なのです。だから、がん腫を取り除いたからといって、決して治癒したことにはならないのです。
この千島論文は、これを認めると、それまでの生物学、遺伝学、細胞学、血液学などの定説を根本からくつがえすことになり、そのインパクトがあまりにも大きすぎたので認められませんでした。
千島博士が実験研究で終始一貫して守り続けた態度は、「書物に学ばず、自然に学べ」という先賢の教えでした。しかも千島博士は自然や生命の中間領域を根気よく観察し続けました。それは、AともBともつかない中間領域に重大な発見のカギがあることをそれまでの経験をとおして知っていたからです。
従来の学者は、とかく明確なものだけを求め、もっとも大切な白と黒との間の灰色の部分、つまり限界領域(中間領域)を無視、軽視しがちでした。しかし、自然や生命の営みはあくまでも連続的であり、Aがいきなりまったく違ったBに飛躍することはありません。変化は徐々に連続的に起こり、変化の過程ではAともBともつかない中間領域が厳然と存在するのです。
数式でシンプルに表された明快な法則を絶対化する研究者たちは、自然のきまぐれな動きのほうを「間違っている」と見ます。それは「書物に学ばず、自然に学べ」とした千島とはまったく反対の、「書物に学び、自然から学ばず」という研究態度です。
がん細胞は細胞分裂によって勝手に増殖するものではなく、劣化して病変した赤血球が集まってがん細胞に分化します。そして、赤血球は食べ物から造られ、しかも意識や感情、心理状態などに多大な影響を受けています。となれば、まずは食べ物に気をつけ、ストレスを溜めこまないようにすることが、がん克服のための中心治療となります。