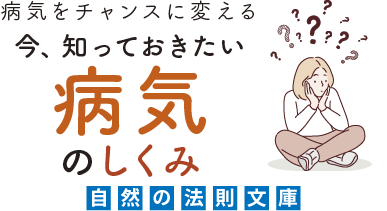加工食品診断士協会の代表理事である阿部司氏は著書『食品の裏側』で次のように書いています。
近年、「超加工食品」という言葉を耳にする機会が多くなりました。
該当するのは大量生産のファストフード、インスタント食品、菓子パン、コンビニやスーパーの弁当や惣菜、スナック菓子、清涼飲料水など、比較的安価で簡単に手に入り、すぐに食べられるように加工された食品を指します。
じつは日本には、世界的に見てもこうした超加工食品が非常に多いのです。その原因は、日本はコンビニ大国であるということです。そのコンビニで売られているのが超加工食品なので、日本で超加工食品が多くなるのはあたりまえなのです。
ヨーロッパにはコンビニはありません。ヨーロッパの人と話すと、「日本人はなぜ自分で作れるものに何倍ものお金を払うのかしら? やっぱりお金があるし、忙しいんだよね?」と言われます。お茶やおにぎりは自分で作れますよね。それをわざわざ買うということに不自然を感じるのです。
近年、「超加工食品」という言葉が注目を集めるようになったのは、2018年にパリ13大学が発表した論文がきっかけでした。約10万人の成人を対象に、インターネットを通じて8年間、食事の追跡調査をした結果、超加工品食品の摂取が10パーセント増加するとがんになるリスクが12パーセント上昇し、45歳以上で超加工食品を多く食べている人の死亡リスクは14パーセントも上昇したということです。
日本では、就学前の幼児肥満の増加が問題となっており、高校生の4割超が生活習慣病予備軍だといわれています。成人のみならず、子どもたちですら食生活が乱れ、健康が危機に瀕しているのです。その大元こそが超加工食品なのです。
超加工食品の盲点は、自分でも作れる食べものに食品添加物が多用されているとは夢にも思わないことです。
家庭の台所には安定剤や防腐剤はありませんし、料理に食品添加物を入れるという発想はありません。ところが、スーパーやコンビニで買うお惣菜には、1品目につき20種類以上の添加物が使われているのが普通なのです。
ほとんどの人は、ふだん、自分が体の中に入れている超加工食品がどのように作られているかを知りません。手軽さの裏には、こうした落とし穴が潜んでいるのです。
科学的に証明されているわけではありませんが、教育の現場では超加工食品をやめて食事を変えれば子どもに落ち着きが出るというのは定説です。幼稚園児ならまず絵が変わってきます。家で貧しい食生活を送っている子は落ち着きがないことが多く、頭が「丸」の針金人間の絵を描く傾向が見られるのに対し、きちんとした食生活をしている子は落ち着いていて、絵も目や鼻や口まで描かれているそうです。
使い古された表現ですが、やはり「あなたはあなたが食べたものからできている」ということです。食べものこそが自分を形成する唯一の要素なのです。